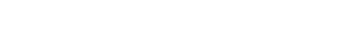ピアノの譜読みの効率良い練習方法を知りたい方向けの記事です。「こどもが譜読みが苦手で、新しい曲に挑戦するのを嫌がる。譜読みの効率よい練習方法を知りたい。ピアノ上達のコツは?」
自分がこどもの時にピアノを習い、2人の子供達のレッスンに10年以上付き合ってきましたが、ピアノを習い始めた子供が早く上達するための近道は、「譜読み」が出来るようになることだと感じています。
練習もあまりしなかったので、長くやった割に、上手くなりませんでした。
その当時は上手くならない原因なんて考えもしませんでしたが、今となっては良く分かります。
こうならない為には、ピアノを始めたばかりの時に、譜読みをしっかり出来るようにしておくのが一番です。
もちろん、もう何年か習っているけどなかなか上達しない、という方にも効果大!です。
譜読みの力は、集中して学習すれば、わりと短期間で習得できます。
ピアノ練習のコツは譜読み!子供が早く上達する方法を解説

ピアノのレッスンを始めて、まず最初に覚えるべきことは、「正しい姿勢」と、「譜読み」です。
これは先生にしっかり見ていただいて、家では先生に言われたとおりに弾けるよう、ママがチェックしてあげるといいですね。
そして、譜読みです。
耳コピで弾いていると、教本(サウンドツリーやバイエルなど)はスイスイ進むのですが、曲が難しくなるにつれて、だんだんとペースが落ちてきます。
すると、練習するのが面倒になって、そのうち練習しなくなる、という悪循環におちいってしまいます。
週1回のレッスンではなかなか譜読みは身に付かない!

音符の学習は、習いはじめのころに、ドとか、レとか、ワークに1回やるだけで、その後は「練習していくうちに楽譜に慣れてね」という流れの先生が多いかと思います。
でも、実際は、何年やっても、譜読みのスピードはそれほど速くなりません。
小学校に入ると、ひらがなを習って、音読をするのと同じように、譜読みも習う必要があります。
ひらがなは毎日接するから早く覚えますが、音符は週1回30分だけ。
なかなか覚えられないのは当然です。
パッと見てどの音符かすぐにわかるくらいまで覚えてしまうと、その後の練習がとてもラクになり、テキストがスイスイ進みますよ。
教本を早く進めることよりも、絶対的に効率がよく、非常におすすめの練習方法です。
譜読みの効率よい練習方法
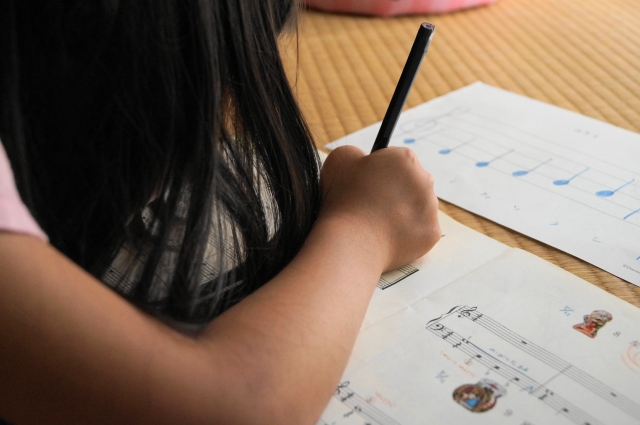
とはいえ、譜読みの練習ってどうすればいいのやら。そこで、譜読みが早く出来るようになる練習方法を解説します。
譜読みの練習 まずは右手のドレミファソ
まず最初の目標は、「ト音記号(右手)のドレミファソ」の楽譜の位置を覚えること
強引なようですが、まずはこれだけを、覚えちゃいましょう!
ドから順にレミファソ・・・と辿っていくのではなく、この場所にある音符は「ド」というように、場所で覚えるのがポイント。
小さい子供でも意外とすぐに覚えてしまいますから、
「うちの子にはまだはやいわー」
なんて言わずに、ぜひ試してみてください。その後のレッスンの進み方が明確に変わります。
「書いて覚える徹底!!譜読」がおすすめ
ある程度おんぷを覚えてきたら、ワークを使って記憶を定着させていきます。
書き込み式になっていますが、別のノートなどに答えを書くと、何度も繰り返し使えます。
「導入編」と「2」というのもありますが、内容は同じで、字の大きさが違うだけです。
うちの子たちは書くのを面倒がって、やだーとか言ってましたから、
音符を指さして、
「これ何?」
「ド」
というように、口頭でやってました。答えもありますから、音符が苦手なママでも大丈夫です。
これだと、1日に3ページやっても、数分で終わります。
うちでは、枕元に置いておいて、寝る前にやってました。
毎日やる、とか決めてしまうと負担になって続きませんから、気軽にやってみてください。
譜読みのワークを進めるのと同時に、レッスンの教本の楽譜は、かならず自分で譜読みさせることが大切です。
「ドはここ」、「レはここだよ」と先回りして教えちゃうと、確かにその曲は早く弾けるようになります。
先生に早くマルをもらえるので、テキストがサクサク進みます。ですが、その後、行き詰まってしまいます。
譜読みやリズムのワークを集中してやらせると、譜読みが本当に早くなります。
ただ、一時的に早くなってもしばらく経つと忘れてしまうので、継続的に身に付くまでやらせることが大切です。
音とリズムは別で考えると混乱しない

楽譜を読んで曲をひくには、音の高低だけではなくて、リズムの理解も必要です。
符点が付いたり、8分の6拍子なんて出てくると、混乱しやすいです。
さらに、曲が難しくなってくるにつれて、どんどんリズムも複雑になっていきます。
ピアノの楽譜で『リズム』がよく分からない方 「子供がリズムがよく分からないみたい、リズムの基礎が知りたい、子供がリズム練習できる本ってあるのかな。」 子供のピアノ練習【リズムが分かる!】おすすめの本を4冊紹介します この記[…]
「練習しなさい」と言わなくても、子供が「自分から毎日練習する習慣」を身に付ける方法を知りたい方 「毎日『ピアノの練習しなさい』と言いたくない。子供がピアノの前に座るまでに時間がかかる。どうすれば毎日の習慣になるの?」 […]
今回は譜読みの重要性とその練習方法についての記事でした。
最後までお読みいただきありがとうございました!